「7月盆」
2024.07.10
-520x390.jpg)
昨日の松江は梅雨前線の影響で記録的な大雨となり、家屋への浸水や道路冠水などが発生しました。今後も引き続き注意が必要になりそうですね。★山陰地方でのお盆は8月に行われますが、関東や東海、北陸の一部では7月15日を中心に「7月盆」が行われます。同じ日本のお盆なのに不思議ですね。江戸時代中期(1704年)に発刊された「華実年浪草」には「七月十三日、黄昏に及びて都鄙倶に聖霊を迎ふるの儀あり、門前に於いて麻殻を折り、焚きてこれを迎え火という」とあります。もともと江戸時代の人々は旧暦の7月に「迎え火」を焚いていたようですね。ではなぜ現在のお盆に1ヶ月の違いがあるのでしょうか? これは明治時代に行われた改暦が関係しているようです。明治6年に新暦が採用されたのに伴い、お盆の時期は地域の生活様式や文化によって分かれ、東京やその他一部地域では7月盆、農村や漁村の多い地方では8月盆が定着したと言われています。地域ごとの様々な事情もあり統一することは難しかったようです。新暦の導入に伴ってお盆の時期は地域により異なってしまったようですが、ご先祖をお迎えして感謝するという大切な行事であることに違いはありませんね。★今年も8月16日には大橋川南詰付近で「灯籠流し供養」が執り行われます。同時に、今年も「盆飾りの供物回収と供養」も行われる予定になっています。
「紫陽花」
2024.06.30

週の後半も梅雨らしい天候が続きました。本格的な夏の到来はもう暫く先のようですね。★この時期になると近くの天台宗寺院「普門院」の境内には紫陽花の花が咲き誇ります。素通りしようと思ったのですが、鮮やかな色合いに思わず見入ってしまいました。 「紫陽花や帷子時の薄浅黄(松尾芭蕉)」 帷子(かたびら)とは裏地を付けない夏用の衣という意味。薄浅黄は浅葱色に近い色で、江戸時代の元禄期から正徳期に流行したそうです。芭蕉の生きた時代の人々も紫陽花のような薄浅黄色の涼しげな衣を身に着けて移りゆく季節を感じたのでしょうか。★松尾芭蕉は江戸時代の俳人ですが、平安時代から鎌倉時代初期にかけて活躍した「西行法師」に強く影響を受けたとされています。西行法師は出家したのち高野山に入り、全国を行脚して多くの歌を詠んだことでも知られています。芭蕉の「奥の細道」の旅の目的も東北各地で俳句を詠むことと同時に、西行法師など先人が歌に詠んだ歌枕の地を探訪するという意味もあったとされます。そして道中では奥州平泉や出羽国立石寺などを巡り数多くの句を詠んでいます。やがて芭蕉が旅した東北・北陸の地は多くの俳人や歌人たちの聖地となり、芭蕉を慕いその跡を辿るようになったとされています。★梅雨空の下で紫陽花を眺めながら、いにしえの人々が生きた時代に思いを馳せると時間が経つのも忘れてしまいますね。
「お盆百科」
2024.06.20
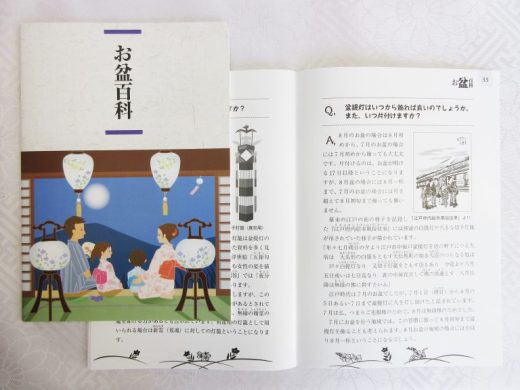
明日は一年を通して昼間の時間が最も長くなる「夏至」。朝の4時半頃には東の空が明るくなっているので実感しますね。★6月の半ばを過ぎると私たちはお盆の準備のお手伝いで慌ただしくなります。お盆のお供え方法などについてのご質問を頂くようになるのもこの時期からでしょうか。特に初めてお盆を迎えるお宅では分からないことも多いと思いますので丁寧にご説明させていただいています。また、当店では【お盆百科】という冊子もご準備しています。お盆に関する疑問や盆棚の飾り方などを分かりやすく説明してあり、読みやすい内容になっています。店頭に置いてありますのでどうぞご自由にお持ち帰りください。★山陰地方では盆棚に「素麺」をお供えされるお宅も多いようです。普段はお供えに用いないので不思議ですね。もともとは七夕にお供えされていた素麺が、やがてお盆の素麺に引き継がれたと考えられています。牽牛(けんぎゅう/夏彦星)と織女(しょくじょ/織姫星)の伝説で知られる七夕はお盆の行事と深い関係があったとされています。古くは素麺を食べると熱病にならないという言い伝えもあり、平安時代の宮中の七夕行事(乞巧奠/きっこうでん)では「熱病除け」として素麺が供物に用いられていたそうです。(参考:お盆百科)★梅雨入りも間もなくでしょうか。週末にかけて雲の多い空模様になりそうな予報になっていますね。
「盆提灯」
2024.06.10

松江では一昨日から降り続いた雨も上がり、今日は青空も見える朝を迎えました。日中の気温も上昇する予報になっていますね。★お盆の時期には少し早いような気もしますが、店内では盆提灯の展示を始めました。盆提灯は画像のような「大内提灯」と呼ばれる足の付いた組み立て式のものが基本形ですが、近年はモダンなお仏壇に合うシンプルな構造の提灯も多くなってきました。★山陰地方では一般に八月のお盆に縁側や玄関口、仏間などに盆提灯を灯しますが、盆提灯はいつ頃から用いられるようになったのでしょうか。古い史料によると提灯は大陸から伝わったとされ、もともとは折りたたみのできない竹籠に紙を張っただけの簡単なものだったようです。藤原定家の「明月記」の寛喜2年(1230年)7月の条には「近年民家にて今夜長竿を立て、その先に燈籠の如きものをつけ、紙を張り、燈をあげて遠近これあり」という記述があることから、鎌倉時代にはすでに家ごとにご先祖の精霊を迎える風習があったと考えられています。★折りたたみ可能な提灯が考案されたのは室町時代の後期で、江戸時代には岐阜地方に産する竹を骨として、特産の美濃紙を張った岐阜提灯が知られるようになり、有数の産地として発展したという記録が残っています。★電気などのない時代には、菜種油などに火を灯す明かりそのものが貴重で、仏前で灯す提灯や燭台の明かりも古くから大切なお供えのひとつだったのかもしれませんね。
